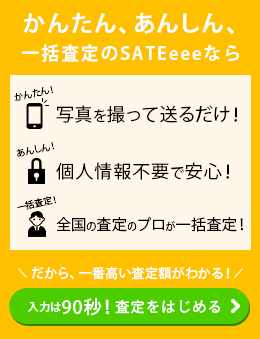古墨(こぼく)を高価買取!書道具の査定ポイントを徹底解説!
1. 古墨(こぼく)を売りたいお客様へ
古墨(こぼく)とは墨の中でも作られてから長い年月が経った質の良い墨のことを指します。中国で作られたものを唐墨、日本で作られたものを和墨と言います。唐墨は清代までに作られたものを、和墨は江戸時代までに作られたものを古墨と言います。できたてのものは墨色が冴えないとされ、20年~100年ほど寝かせたものが最もよい墨色だとされて言います。 墨は文房四宝にも数えられ、昔から珍重されてきました。そのため質が良く、保存状態の良いものは書道家の間で人気となっています。2. 古墨(こぼく)についての解説
古墨とは製造から10年以上が経った墨のことです。年数が経つと、墨の粘りであるニカワが落ち着いてより良い墨色になることから寝かすほど良いとされています。また古墨は微妙な墨色も再現できることから、書道家の間でも人気です。 しかし寝かすほど良いと言っても、100年以上経過したものは実際の使用には向いていません。またただ墨を寝かせれば良いというものではなく、よい原料とよい製法が不可欠です。そのため製法が悪ければ古墨とは呼べません。 手間をかけて手作業で煤を練り上げる昔ながらの墨の製法は現代ではほとんど見られなくなり、古墨も手に入れづらくなっています。3. 古墨(こぼく)の歴史
古代中国の甲骨文や殷王朝の遺構から墨書きされたものが出土していることから、この時代には既に墨があったと考えられています。固形の墨が登場したのは、漢代に入ってからです。当時の原料は松煙と石墨、ニカワ、香料であったとされます。 唐の時代になると李超・李廷珪親子、明代には程君房(ていくんぼう)、方于魯(ほううろ)などが名工と言われていました。このころは品質も優れた墨が多く作られており、造墨の頂点だとも言われています。特に清代まで原始的な製法で作られていたため、煤の品質は非常に良いものでした。しかしその後、重油や灯油などの煙が使用されるようになり、品質は下がる一方になります。現在では大量生産による低価格化が進み、昔のような墨作りの後継者は少なくなりました。4. 古墨(こぼく)の代表作や作者
- 乾隆御墨
- 敬勝斉蔵墨
- 龍鳳呈祥
5. 古墨(こぼく)の買取査定ポイント
古墨は品質がとても大事です。近年の大量生産品は手作りのものよりも質が良くないため、作られた年代や作者が重要な査定ポイントです。また保存状態が良いか、箱はあるかなども大事なポイントとなります。 代表的な査定ポイント- どの時代の誰の作であるか(証明書や鑑定書があれば尚良し)
- 作者の署名(印・銘)があるか
- 保存状態は良好か(欠けがない、箱が残っているかなど)
- 大きさはどれくらいか
6. 古墨(こぼく)の取引相場価格
古墨の相場価格は保存状態や年代によって大きく異なりますので、1~10万円と幅があります。 例えば「壬午年海陽 方于魯珍蔵」と刻印のある中国の古墨には約11万円の値がつきました。こちらは、縦約96.4mm、幅約33.5mm、重さ約35.5gで、墨特有のカビや汚れ、ヒビなどがありますが、保存狀態は良好です。表面に細かい細工が彫られています。 また清台の古墨で「「養性殿珍蔵」、「龍徳」、「玉府永蔵」篆書鍍金と彫ってあるものには、約3万円の値がつきました。こちらは重さ226gで、龍が彫られています。7. 古墨(こぼく)の買取についてのまとめ
製造されてから10年以上経過したものを古墨と言います。新品の墨よりも粘りが落ち着いてよりより墨色を見せることから書道家の間で人気があります。また運筆も良く、墨色表現もしやすいと言われています。 10年以上寝かせたものでも、ものの原料や製造方法が良くないと古墨にはなりません。また100年以上経ったものは実用品としての使用には向いていません。 しかし骨董品としては価値があるため、保存狀態が良く、表面に彫刻が施されているものであれば高額査定の可能性もあります。品物の取引相場価格を検索
お手持ちの品物名や作者などご入力し検索をすると、品物の取引相場価格や品物情報などを閲覧する事ができます。
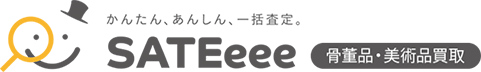
 仏教美術
仏教美術 中国美術
中国美術 香道具
香道具 書道具
書道具 剣・日本刀・槍
剣・日本刀・槍 装具・金工品・皇室下賜品
装具・金工品・皇室下賜品 伝統・工芸品
伝統・工芸品 万年筆
万年筆 腕時計
腕時計 掛け時計
掛け時計 懐中時計
懐中時計 ライター
ライター 洋食器
洋食器 楽器
楽器 レトロおもちゃ・ソフビ人形
レトロおもちゃ・ソフビ人形 宝石
宝石 象牙
象牙