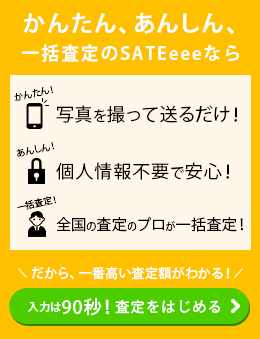香合(こうごう)を高価買取!皇室下賜品の査定ポイントを徹底解説!
1. 香合を売りたいお客様へ
香合とはお香を入れる蓋付きの器のことを指します。茶道具の一種ですが、仏具の一種としても数えられます。これはお香が仏教と共に伝来し、もともとは仏前で焚かれていたことに由来します。茶道での香合はお香を入れておくための器として使用されます。お湯を沸かす炭点前でお香を焚いたり、床の間に飾ったりして使用します。季節などにより香合の種類を変えることもあります。 香合は様々な素材で作られており、特に象牙などでできたものは高値で買取される場合もあります。2. 香合についての解説
香合とはお香を収納する蓋付きの小さな容器で、茶道具・仏具の一種です。茶道具での香合は、茶事においてとても重要な存在です。炭点前の時は、亭主に所望して香合を拝見します。また床の間に飾って使われる場合もあります。季節によってお香と主に香合の器などを使い分けることが多いです。5月~10月間は風炉と言い、唐木・竹製などの漆器の香合と角割の香木を用います。そして11月~4月の間は陶磁器の香合と練香を用います。またハマグリなどの貝類や金属類は、季節を問わず使われます。 仏具においての香合は、焼香や抹香などを入れて使用し、仏前で焚かれたりしていました。3. 香合の歴史
日本へは仏教と共に伝来したとされています。904年に建立された仁和寺円堂の跡から合子が出土したことから、この頃には使用されていたと言われます。また南北朝時代の「喫茶往来」や室町時代書物に「香合」という名称が記されています。 さらに1542年の茶会記である「松屋会記」にも香合のことが記されており、この頃には茶道具として台頭していることが伺えます。また江戸時代中期頃には香木を使用したお香が焚かれるようになりました。 近代でも香合は作られており、明治・大正時代には人間国宝の手による名品がいくつも誕生しています。4. 香合の代表作や作者
- 伽藍石香合 桃山時代
- 織部六角蓮実香合 桃山~江戸時代
- 撫子蒔絵錫縁香合 桃山時代
5. 香合の買取査定ポイント
香合は陶磁器、漆塗り、金属、はまぐりなど様々な素材から作られています。そのためどの素材で作られているかは重要なポイントです。また蒔絵や象嵌が施されたものなどは、美術品としての価値も高くなります。 また保存状態の良いもの、どの時代に作られたものかも査定のポイントです。 代表的な査定ポイント- どの時代、どの作者の作品であるか(証明書や鑑定書があれば尚良し)
- 作者の署名があるか
- 保存状態は良好か(箱が残っているかなど)
- 尺はどれくらいか(大きさの確認)
6. 香合の取引相場価格
香合は素材や作者、時代によって値段に差が出てきます。例えば人間国宝の松田権六作の香合は約45万円の値がつきました。こちらは漆塗りで千鳥蒔絵が描かれているもので、高さは2.8cm、直径は5.5cmのものとなります。また堆朱楊成作の高さ約2.5cm、直径約6cmのもので箱付きの香合は約36万円となっています。 もし茶道具一式が揃っていてそれぞれに蒔絵が施されたような品物ですと、100万円を越す場合もあります。7. 香合の買取についてのまとめ
香合は茶道具の一種として数えられる道具です。その名の通り、お香を納めるもので、様々な素材から作られています。季節によって香合やお香種類を変えることで、季節の移り変わりを感じることができます。また仏教徒と共に伝来したことから仏具の一種としても数えられており、元々は供え香として仏前で焚かれていたとされます。 珍しい象牙や、有名な作家の手によって作られた香合は高額査定になる可能性もあります。品物の取引相場価格を検索
お手持ちの品物名や作者などご入力し検索をすると、品物の取引相場価格や品物情報などを閲覧する事ができます。
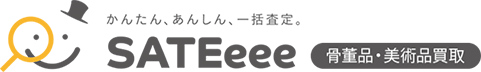
 仏教美術
仏教美術 中国美術
中国美術 香道具
香道具 書道具
書道具 剣・日本刀・槍
剣・日本刀・槍 装具・金工品・皇室下賜品
装具・金工品・皇室下賜品 伝統・工芸品
伝統・工芸品 万年筆
万年筆 腕時計
腕時計 掛け時計
掛け時計 懐中時計
懐中時計 ライター
ライター 洋食器
洋食器 楽器
楽器 レトロおもちゃ・ソフビ人形
レトロおもちゃ・ソフビ人形 宝石
宝石 象牙
象牙